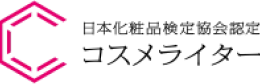少しづつ温かくなり、春が来ると少しわくわくする反面、肌荒れが気になる季節でもあります。もしかしたらそれは花粉が原因かもしれません。
花粉による影響は、鼻水やくしゃみといった身体的な影響が目立ちがちかもしれませんが、肌への影響が出てしまう人も実は多くいるのです。
季節の変わり目のタイミングでもあるので、花粉が原因ということに気付きにくい場合もあります。肌荒れの原因を知ることは美肌を目指すためにも大切なこと。きちんと対策をして花粉による肌荒れを未然に防ぎましょう。
花粉の種類が最も多い4~5月
4月~5月は花粉の種類が最も多く、約4種類の花粉が猛威を振るっているそう。
4月はスギ花粉に加え、ヒノキ花粉もピークを迎えると言われています。そして5月に入ると今度はイネ花粉がピークに。また、季節の変わり目は、花粉がなくても肌荒れが起きやすいものです。
花粉の種類、飛散量が増えることで、肌荒れに悩まされる事も自然と増えてしまいます。目に見えて肌荒れしているなと分かる火照りや赤みなど。いつもより肌が乾燥している、痒みがある気がするといったささいな変化にも注意しましょう。花粉が原因で肌がゆらいでいる可能性があります。正しく対処しないと肌荒れを深刻化させることがあるでしょう。
花粉でなぜ肌荒れが起きるのか
花粉による影響は、体内に侵入した異物を排除しようとする免疫反応によるもの。どのような影響がでるかは人それぞれ違いますが、免疫機能が異物(花粉)に対して過剰に反応することにより引き起こされます。
このメカニズムは、花粉によって肌荒れが起きてしまう場合も同様です。毛穴から侵入した異物(花粉)を排除しようとするために免疫機能が作動、肌荒れを起こします。
本来、肌の表面は皮脂膜という薄い膜で守られており、花粉など外からの刺激から肌を守っています。これが、もともと肌が持っているバリア機能です。肌内部のうるおいを保つことが難しくなり、バリア機能が低下。花粉などの異物が肌内部に侵入しやすい状態になってしまってしまうのです。
花粉で肌荒れを起こさないための対策
花粉で肌荒れを起こさないためには、毎日の適切なケアが大切です。
スキンケアとインナーケアを強化し、外側と内側の両方からアプローチしていきましょう。
スキンケア編
花粉による肌荒れを防ぐために特に意識したいのが、「汚れをきちんと落とす」「保湿ケア」の2つです。
汚れを落とす時に気をつけたい事

肌に付着した花粉を速やかに洗い流す必要があります。外から帰宅したら、なるべく早く顔を洗うとよいでしょう。クレンジングや洗顔はその日のメイクに合わせて選ぶ。クレンジングは洗浄力が高ければいいという事ではありません。過剰に油分を落としてしまうとバリア機能の低下を引き起こします。またクレンジングや洗顔時に肌をこするような洗い方はNGです。やさしくメイクとなじませたり、たっぷりの泡を転がすイメージで、優しく洗うのがポイントです。肌が敏感なこの時期は「低刺激タイプ」「敏感肌処方」のアイテムを選ぶのもおすすめです。優しく落とす、ということを意識して肌を守りながら不要な汚れなどはきちんと落としましょう。
保湿ケアで大切にしたい事

バリア機能にとってもうひとつ欠かせないのが保湿ケアです。肌の水分量が低下すると細胞と細胞の間に隙間ができ、角層のうるおいを保つことができずにバリア機能を低下させてしまいます。乾燥しやすく、花粉による刺激で肌荒れしやすい季節は、気合いを入れて保湿ケアしましょう。
今日から手軽にできるケアとしては、ローションパックがおすすめです。肌の乾燥が気になるときは、いつもより多い量の化粧水をたっぷりなじませましょう。乳液やクリームでうるおいを逃さないようしっかりフタをすることもお忘れなく。
【優れた保湿力を持つヒアルロン酸】
また保湿ケアにおすすめの成分のひとつに「ヒアルロン酸」があります。ヒアルロン酸は、わずか1gで約6Lもの水分を抱え込むことができると言われています。その高い保水力から、多くの化粧品に使われているため、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。保水力が高いということは水になじみやすい性質があるという事。ヒアルロン酸が配合された化粧水、美容液、ジェルなどを選びましょう。
化粧水をいつもより多めになじませた肌にヒアルロン酸配合のパックを使用するのもおすすめ。角層が水分で満たされた状態なので、水になじみやすいヒアルロン酸が浸透しやすくなります。
しかし、高分子のヒアルロン酸には注意が必要。分子量が大きいため角層最深部には浸透しにくいため、この方法では角層に浸透しません。もちろん、化粧水や美容液として塗布したときに効果がないという意味ではありません。角層最深部まで浸透できなかったとしても、肌表面になじんでうるおいを守る事が期待できます。
【ヒアルロン酸を浸透させる様々な技術】
しかし、ヒアルロン酸を角層最深部まで浸透させる事で高いうるおい維持効果が得られます。ですので、化粧品メーカーはヒアルロン酸を低分子化する技術を発展させてきました。化粧品メーカーとは異なるアプローチに、高分子のままヒアルロン酸を届ける技術「マイクロニードル」があります。ヒアルロン酸や美容成分でできた微細な針が角層を押し広げ、高分子ヒアルロン酸を浸透させます。
ヒアルロン酸ほか、コラーゲン、コエンザイムQ10やプロテオグリカンも高分子と言われる美容成分。分子量が大きく、角層内への浸透が困難だった成分も、マイクロニードルパッチなら届けられます。
インナーケア編

スキンケアと同時に意識したいのが「腸内環境」です。腸は体内の免疫の中枢でもある重要な器官。「腸活」という言葉をご存知の方も多いと思います。これは、腸内環境を整えることで免疫力を高める活動を意味します。腸活により、アレルギーなどの炎症を予防・緩和できるかもしれません。
実は、年々花粉に悩む人が増えてきているそう。そしてこれは、食生活の変化に伴うものとも言われています。いわゆる伝統的な日本食には穀類や野菜、味噌など腸の栄養となるものが多く含まれていました。しかし現代では欧米化し、脂質や動物性たんぱく質が多く、腸内の菌バランスが乱れやくなりました。結果、免疫機能が正常に作用しなくなり、花粉による影響を受ける人が増えているようです。
腸内環境を整えるために必要なのは菌のバランスを整えること。腸内の菌は、大きく「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の3種類に分けられます。善玉菌は身体を守り、悪玉菌は増えると身体に悪影響をもたらします。日和見菌は善玉菌にも悪玉菌にもなるという性質を持っています。この3種類のバランスを保つことで腸内環境が安定するのです。
善玉菌を増やすには
善玉菌が十分にあれば悪玉菌の増殖は抑えられます。そのため、善玉菌を増やすことを意識したケアをすることが、腸内環境改善の近道と言えます。
その善玉菌の増殖に欠かせないのが「乳酸菌」です。乳酸菌と聞いてすぐにイメージしやすいのはヨーグルト。乳酸菌は胃酸に弱いという性質があるため、朝食の食後に食べるのがおすすめです。さらに、食物繊維は乳酸菌のエサになるため、腸内できちんと働くためには無くてはならない存在です。
食物繊維と、食後に乳酸菌を摂ることを意識し、これを毎日継続しましょう。腸内に棲みつくことのできる菌の量はあらかじめ決まっています。つまり、一度にたくさん摂取しても、過剰な分は体外に排出されてしまうのです。毎日の積み重ねが大切なので、ぜひ継続して腸内をきれいにしていきましょう。
DHAやEHPで花粉対策
花粉時期のインナーケアとして、魚も意識して摂ることをおすすめします。
「ヒスタミン」というアレルギー物質の働きを抑えてくれる栄養成分が含まれるためです。ヒスタミンは花粉により起こるアレルギー反応の原因物質。この働きを抑制することで花粉による影響を緩和が期待できるでしょう。抑制が期待できる栄養成分には、特にサバやイワシなどの青魚に含まれるDHAやEHPがあります。
インナーケアはスキンケアと同様に、毎日欠かさず行う事が結果に繋がるのです。今日明日で効果が実感できるものではありませんが、毎日続けることをしっかり意識してみてください。